ファイナル平野政吉美術館
- 藤田嗣治の祈り 平野政吉の夢
まだ雪の残る3月に秋田を訪れたとき、ツイッターにて、平野政吉美術館にて藤田嗣治の「秋田の行事」を観るのもこれで最後だろうと書いた。ところがはからずも最後の最後にまた訪れることができたのは幸いだった。6月30日いっぱいで平野政吉美術館は閉館し、藤田作品は、久保田城のお堀をはさんだ向い側(外側)にある新秋田県立美術館に移されるのである。同館最後の展覧会「藤田嗣治の祈り 平野政吉の夢」が開催中だった。
今回も帰りの新幹線時間までの空き時間を利用して観ることが叶った。平野政吉美術館がいかなる経緯で藤田作品を収蔵展示するミュージアムとして建てられたのか、それがわかるいい企画であった。
それによれば、もともと実業家平野政吉が蒐集した藤田作品を展示するために1936年に美術館建設が計画され、藤田はその壁を飾るため、あの大作壁画「秋田の行事」を制作したのだという。ただし建設は戦争によって中止になった。
その後1967年に秋田県立美術館(いまの平野政吉美術館)が建てられるが、そのさい渡仏した平野政吉の関係者にフジタは、「秋田の行事」を見せる空間・建物として、礼拝堂のようなつくりを提案したのだという。たしかに言われてみれば、いまの美術館の建物のトンガリ屋根は礼拝堂のようだ。
このほど、戦前に計画された美術館の青写真(設計図)が見つかり、展示されていた。いずれ秋田大学の先生によってCG再現され、新美術館にてお披露目されるとのこと。それを見ると、いかにも西洋建築らしい(というと表現力の乏しさが露呈するが、庁舎のような神殿風)建物である。
わたしが平野政吉美術館をはじめて訪れたのは2006年10月のこと(→2006/10/30条)。以来秋田を訪れたときに帰りの時間に余裕があれば足を運び、「秋田の行事」が飾られた空間にゆったりを身を委ねて出張の疲れをそこで癒して東京に帰ったものだった。
今回がこの空間で「秋田の行事」を観る最後の機会と思うと、なかなかギャラリーから離れがたい思いを抱いたが仕方がない。9月28日に本オープンを迎える新県立美術館において、「秋田の行事」がいかなる空間で展示されるのか、フジタの絵をどんなふうに観ることができるのか、設計した安藤忠雄さんに期待して*1、冬以降の再訪を期したい。
殺害現場だけご当地
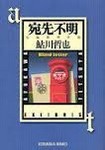
鮎川哲也さんの長篇『宛先不明』*1(光文社文庫)を新刊で買っていたにもかかわらず、ブックオフで先日うっかりダブりで買ってしまった。文庫に入ったのは2010年7月だから約3年前。そのくらい経てば忘れるのもやむを得ないかもしれないけれど、そもそも買って読んでいないのがいけない。もっとも、その頃鮎川作品にそれほど執着していなかったはずなのに、これにかぎって買っていた理由もよくわからない。
先日秋田に出張に行ったとき、この本を携えていったのも、この長篇での唯一の殺人事件(遺体発見現場)が、久保田城(秋田城)跡にある千秋公園であるからだ。ダブりに気づいたとき、パラパラめくってそのことを知り、次に秋田へ行くときに読もうと思っていたのである。
250頁ほどのそれほど長くない作品だが、結局秋田にいるうちに読み終えることができず、東京に戻って数日、ようやく読み終えた。殺人はこの千秋公園での一件きりというシンプルなアリバイ崩し物。千秋公園で殺人をおかすためには東京から夜行列車に乗らなければならず、しかし夜行が出発したあとの時間帯に犯人と疑われる人間の鉄壁のアリバイが立ちはだかる。
そもそも千秋公園の場面は遺体発見のそのときだけで、とても「ご当地(旅情)ミステリ」とは言えない。きっかけは「ご当地」だったかもしれないが、それで読んでみると意外に面白いのでよかった。
ところでいま述べたようなアリバイ崩しの色合いと書名がどう関係するのか。わたしも読みながら不審に思っていたが、まあ心配する必要はない。これ以上説明するとネタばらしになってしまうからここで止めておくが、巻末に収められた作者の「創作ノート」によれば、書名に悩んでいたところに放たれた奥様の助言がそのまま書名に採用となったという。「例によって題がうかばずに七転八倒していると」
とあるので、鮎川さんは書名を付けるのに苦労するほうの作家だったらしい。
松本清張とくらべると、タイトルが直截的な印象を受けてしまうのも、そうした個性に由来するのかもしれない。以前も思ったが、松本清張のように抽象的すぎるほうがかえってミステリのタイトルとしてふさわしいのかもしれない。トリック自体は、東京という大都市の特性が生かされているもので、その着眼点に感服したのだった。
連句による百間作品

東雅夫編『百間怪異小品集 百鬼園百物語』*1(平凡社ライブラリー)を読み終えた。
内田百間はアンソロジーに適合的な作家である。まず一篇一篇が長くない。短いながらもまとまっている。幻想的な小品からユーモアに満ちた随筆、都会の隙間にひそむ妖異から幼時の岡山という地方の土俗まで、バラエティに富んでいる。
講談社版・福武書店版の全集のほか、単行本別に文庫化された旺文社文庫版、テーマごとに再編集された福武文庫版・ちくま文庫版、幾度となくまとめられ、文庫化されている。そこでアンソロジストの東さんは一計を案じた。百物語の形式で小品集を編むということ。
方針として立てたのは次の四つ。怪異小品の趣きのある作品を、小説・随筆・日記に関係なく採録。分量は代表作「冥途」のそれを上限の目安とする(つまり無闇に長いものは避ける)。抄録はしない。連歌・俳諧の付合のようにモチーフの連なりを重視して並べる。かくしてこれまでとはまったく相貌の異なる百間文集ができあがった。
散々百間作品を読んできたつもりであったが、このようにいったんばらして連句のようなつらなりであらためて読んでみると、妙に新鮮である。『冥途』『旅順入場式』収録作品がデビュー直後のものには思えないほど老練であり、日記や随筆もまた創作に負けない幻想味を湛えている。あえてバラバラに配置された『東京日記』が、都会的幻想を語る最高の小説集であることを実感した。百間の怪異を語る語り口が映画的な視点、たとえばクローズアップの手法を用いて効果を出したり、また読む者の五感を巧みに働かせるようにしむけたりしていることをいまさらながら知ったのもありがたかった。オノマトペの使い方もユニークだ。川上弘美さんの世界へと受け継がれている。
わたしは“初出一覧好き”である。こうした作品集に初出一覧があると、一篇を読むごとにその初出媒体を確かめずには済まない性分である。でも今回ばかりは巻末の初出一覧を見ることをぐっと我慢した。そうした情報を頭に入れず、ただただテーマのつながりの妙と意外性を楽しみながら読みつづけるのが、この本の愉しみ方なのだろうと感じたからだ。でも少しだけ初出一覧に注文を出せば、初出媒体・年月だけでなく、収録単行本も示してほしかった。
百物語の最後に配された『東京日記』の「その二十」はこんな出だしである。
湯島の切通しに隧道が出来て、春日町の交叉点へ抜けられると云う話なので、その穴へ這入って見たが、…(344頁)この「隧道」はいまや都営地下鉄大江戸線として実現してしまっている。何とも恐ろしいではないか。でも百鬼園先生が描くところの「地下世界」は、たんにレールが引かれているだけではないのだが。
府中には長谷川利行がある

- 近代洋画にみる夢 河野保雄コレクションの全貌@府中市美術館
土日に出張があった代休を利用して、府中市美術館に行く。前回のデルヴォー展のおりは車で行き、渋滞で往復に苦労したので、今回は京王線とバスを使う。最近美術館の展覧会情報はネット経由で知ることがほとんどだが、この展覧会はそうでなく、漱石特集のため久しぶりに購入した『芸術新潮』6月号によって知った。『芸術新潮』を買わなかったらどうなっていたのだろう。
それほどに期待をはるかにこえて素晴らしく充実した展覧会だった。河野保雄というコレクターの名前はまったく知らなかった。『芸術新潮』には長谷川利行17点・関根正二11点とあり、これにまず惹かれた。府中市美術館のサイトで調べてみると、河野コレクションは、洲之内コレクション・窪島誠一郎コレクションに比肩するとあって、ますます関心が高まった。
しかも、堀江敏幸さんの処女長篇『いつか王子駅で』*1(新潮社)のカバーを飾る長谷川作品「荒川風景」は府中市美術館蔵だったと記憶していた。とすればこの絵も河野コレクション中の一点である可能性が高い。そもそもわたしが長谷川利行という画家を意識しだしたのは、2001年に出た『いつか王子駅で』であったように思う。だから「荒川風景」は、わが“長谷川利行好き”の原点に位置する作品なのだ。
会場に入るといきなり長谷川利行作品がずらりと並んでいる。そこに当然「荒川風景」もあった。興奮せずにはいられない。そこからギャラリーの奥を見通すと、壁面にぎっしりと絵が掛けられている。通常絵の展覧会は壁面をゆったり使うことが多いが、そんなことをやっているとすべて展示できないという雰囲気の陳列なのだ。どちらが良くてどちらが悪いというわけではない。こんなふうにぎっしり絵が詰まっているのは、この濃密さのなかにこれからどんな素晴らしい絵が先にあるのだろうという期待をさらに増幅させる効果があった。
長谷川利行は「荒川風景」はもとより、いかにも利行らしいタッチとマティエールの「カフェの入口」もいいし、水彩の「川のある風景」「中華料理店」も一目で利行だとわかる描き方で好ましい。しばしこれら作品の前に佇んだ。帰宅後図録を見ると、河野氏のコレクターとしての出発は長谷川利行作品の蒐集により、100点以上を集めたのだという。
そうして集めた長谷川作品を売って(どの程度売ったのかわからない)購入したのが、同郷福島出身の画家関根正二の「一本杉の風景」だった。関根正二は、東京国立近代美術館の「三星」が印象深く、人物画が多いのかと思っていたら、この「一本杉の風景」のほか、人物画の画風とはおよそ異なる味わいのある「牛舎」などもあって、多少これまでのイメージが変わった。
そのほか、青木繁・小出楢重・萬鉄五郎・中村彝・岸田劉生・村山槐多・木村荘八・恩地孝四郎・野田英夫・松本竣介・清水登之・靉光など好きな画家の作品がずらりと並び、堪能した。小品ながら野田英夫の「壁画下絵」はいつものモンタージュ画法を用い、哀感が漂ういいものだった。
河野氏はガラス絵蒐集にも熱心で、これは子供のときに出会った思い出の延長線上にあるという。ここにも長谷川利行のガラス絵が7点。割れているものもあるが、名刺大よりひと回り小さいガラスに描かれた「T・H」の極小品も捨てがたい。
版画では谷中安規と長谷川潔。とりわけ今回は長谷川潔のメゾチント版画の風合いに見とれる。石版画の冷たさとも異なる「アレキサンドル三世橋とフランス飛行船」「セードルの実のある静物画」の質感は、どうやって出すのだろう。
洲之内コレクションの場合、一人の画家につき作品数はあまり多くない。ある特定の画家を集中的に集めるということはないのである。いっぽう河野コレクションにはある特定の画家、ある特定のジャンル(ガラス絵など)に沿って多くの作品が収められている。コレクターの個性もさまざまだが、河野コレクションのようなばあい、そのコレクターの好みと、観る立場のそれが合致したときの喜びは絶大なものがある。だから今回わたしはこの展覧会を観ることができて幸せだった。
河野氏は音楽評論家から出発し、福島で貸しビルや水商売を営んだ実業家であり、馬主でもあったという。そこで得た財が、自らの情熱と感性にもとづいて芸術作品に投ぜられたというのは素晴らしいことである。しかもそれらがある程度まとまって府中市美術館や福島県立美術館に譲渡されたことも大きい。
コレクター河野保雄氏の足跡をたどることもできる図録(2000円)は必携であり、巻末のコレクション総目録(全点小さいながら図版あり)も貴重資料だ。これを見ると、展示されていない長谷川利行作品が府中市美術館にはあって(「浦安風景」「三河島風景」など)、いつの日か、と思わずにはおれない。
風の吹きまわし

ナサニエル・ウェスト(丸谷才一訳)『孤独な娘』*1(岩波文庫)を読み終えた。
翻訳小説はとんと弱く、その第一の理由は外国人の名前がおぼえられない。だからほとんど読まない。それでも若い頃は何とかカタカナ書きになっている人の名前も頭に入ってきた。最近もたまに気が向いて購入するけれど、読んでみるのはたいがいミステリだ。でもそれも通読しないで途中で挫折してしまう。そんな翻訳小説が苦手なわたしでも、丸谷才一訳というふれこみには弱い。書棚を見やると、ブリジット・ブローフィ(丸谷才一訳)『雪の舞踏会』*2(中公文庫)なんていう本がある。丸谷本おなじみの和田誠さんのカバー。2010年に買ったが読んでいない。
最近買った『孤独な娘』もおなじ丸谷訳ということで、『雪の舞踏会』と一緒に丸谷本コーナーに差していた。たまたま電車で読む本を探していて、出かける時間まであまり間がなかったために、慌てて書棚から抜き出したのがこの本だった。丸谷訳、薄め(200頁に満たない)というのが決断の決め手だったかもしれない。岩波文庫なので残念ながら和田さんのイラストはない。
作者のウェストは37歳という若さで亡くなったアメリカの小説家。この『孤独な娘』は1933年に刊行された代表作だという。新聞紙の身の上相談欄を《孤独な娘》というペンネームで担当する「男性記者」が主人公。
彼のもとに寄せられる「身の上相談」は、貧困や性的暴力など悲惨なアメリカ下層社会を映し出していく。1930年代の大都会ニューヨーク。ウェストが書く人間模様や社会模様にさまざまあれど、もっとも気になったのは次のくだりだった。
とりまいている柵には、今日の事件を書いた紙が貼りつけてある。母親、斧で五児を殺す。七児を殺す。九児を殺す……ベーブ・ルース、二本かっとばす。三本かっとばす……。(70頁)そうか、この《孤独な娘》はベーブ・ルースの同時代人なのか。この小説に登場する人びとは、大都市のなかで喘ぎながら暮しているいっぽうで、ベーブ・ルースのかっとばすホームランに歓喜していたのか、ということ。
調べてみると、1930年代初頭のベーブ・ルースはもうほとんど選手生活の晩年に近かったようだが、ホームランを「かっとばす」と表現されるほどの量産はしていたらしい。一時期彼は投手と打者を兼任していたという。そういえば、病気の子供にホームランを打つと約束して、本当にそれを実現したという逸話もあったっけ。これなどは、『孤独な娘』で描かれた世界に案外通じているのかもしれない。
アリバイ崩しのむずかしさ

鮎川哲也さんの『憎悪の化石』*1(角川文庫)を読み終えた。本書は、『黒い白鳥』*2(創元推理文庫)とともに日本探偵作家クラブ賞を受賞したということで、その意味ではこの二作がおなじ年(1959年)に書かれたのは奇跡的である。
容疑者のアリバイを自らの足でこつこつと調べて回る刑事たちが主人公だからか(そういうミステリだからか)、1959年、ひいては昭和30年代という世相を感じさせる描写が多く、読んでいてとても面白い。
殺人事件の被害者は独身で、一時期大阪にいたことがあるという。被害者の身辺から犯人を割り出すため彼の女性関係を洗おうとする。そこで「もし必要ならば大阪警視庁に調査を依頼しよう」
という言葉。警視庁とは東京都警察のみを指すことばのはずと訝って調べると、戦後1947年に置かれた大阪市の自治体警察大阪市警察局が1949年に大阪市警視庁と改称し、全国の自治体警察が廃止される1954年まで存続したという。時代考証に厳密にいえば、したがってこの長篇の時間的舞台はこの期間に限定されることになる。
熱海署の刑事たちが東京に捜査に行くとき、熱海始発東京行の湘南電車に乗り込む。そのとき老刑事は、座席をとろうと殺到する団体客につきとばされてホームから転落しそうになり「今日はついてなさそうだ」と苦笑する。そんな観光地の光景。そして前回関川夏央さんの『昭和三十年代演習』のときも書いた、都電や隅田川の悪臭に対する悪態ともいうべき批判。
またたとえば、戦災をまぬがれた地域に対するまなざしもいまとなっては貴重である。
天神下でおりた。このあたりは大正の震災にも今度の空襲にも難をまぬかれて、むかしのままの様子をのこしているといわれている。鷗外の「雁」の舞台がこの裏側あたりであり、お玉が住んでいたようなしもたやが一帯に軒をならべているという話を、伊井はなにかで読んだ記憶がある。(88頁)
彼が焼けた家や椎の大木を思い出したのは、千駄ヶ谷のあちらこちらにまだ空襲のあとがそのまま残っているからである。東京のどこもかしこも復旧がなり、なかには戦前以上ににぎやかになった場所も少なくないのに、この一帯に、忘れられたようにとりのこされた地点があるのがふしぎであった。そして、それよりもなおふしぎなのは、戦前は上品な邸宅街として知られたこのあたりに、いわゆる温泉旅館というものがニョキニョキと建って、いまでは千駄ヶ谷ときくと連れこみ宿を連想するほどになったことだった。(101頁)この湯島や千駄ヶ谷に対する感慨を抱く伊井刑事は、戦前「旧都内」に住んでいたから、戦後の東京の変貌ぶり(あるいは不変ぶり)に鋭く反応する。
先の引用のように、伊井刑事は湯島天神下を訪れたとき鷗外の「雁」を思い出す。別の場面では、別の刑事が築地の水上署を訪れたとき、
「杢太郎の作品をよんで、明治時代のこのあたりに異人館がたくさんあったことを彼は知っている」と感想を洩らす。鷗外といい杢太郎といい、刑事もたくさん文学作品を読んでいる。これもまた『昭和三十年代演習』の話だが、関川さんは松本清張の「張込み」に触れ、そこで若い刑事(映画では大木実)が佐賀まで向かう汽車のなかで「文庫本の翻訳の詩集」を読むことに驚いている。文学趣味というより、この時代はこうしたことがあたりまえだったのだろう。
ところで本書は帯の袖にアリバイ崩しのミステリであることが紹介されている。解説に先に目を通そうとしてめくろうとしたら、巻末附録として時刻表が掲載されていた。犯人が鉄道を利用したアリバイを主張している人物であることを暗示(というより明示)しているではないか。そんな大それたことをしてしまっていいのだろうかと、筋を追う興味をなかば失いかけたが、心配ご無用。なるほどというひねりが加えられており、さすが鮎川さんと思わせる。