殺害現場だけご当地
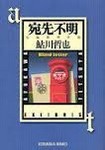
鮎川哲也さんの長篇『宛先不明』*1(光文社文庫)を新刊で買っていたにもかかわらず、ブックオフで先日うっかりダブりで買ってしまった。文庫に入ったのは2010年7月だから約3年前。そのくらい経てば忘れるのもやむを得ないかもしれないけれど、そもそも買って読んでいないのがいけない。もっとも、その頃鮎川作品にそれほど執着していなかったはずなのに、これにかぎって買っていた理由もよくわからない。
先日秋田に出張に行ったとき、この本を携えていったのも、この長篇での唯一の殺人事件(遺体発見現場)が、久保田城(秋田城)跡にある千秋公園であるからだ。ダブりに気づいたとき、パラパラめくってそのことを知り、次に秋田へ行くときに読もうと思っていたのである。
250頁ほどのそれほど長くない作品だが、結局秋田にいるうちに読み終えることができず、東京に戻って数日、ようやく読み終えた。殺人はこの千秋公園での一件きりというシンプルなアリバイ崩し物。千秋公園で殺人をおかすためには東京から夜行列車に乗らなければならず、しかし夜行が出発したあとの時間帯に犯人と疑われる人間の鉄壁のアリバイが立ちはだかる。
そもそも千秋公園の場面は遺体発見のそのときだけで、とても「ご当地(旅情)ミステリ」とは言えない。きっかけは「ご当地」だったかもしれないが、それで読んでみると意外に面白いのでよかった。
ところでいま述べたようなアリバイ崩しの色合いと書名がどう関係するのか。わたしも読みながら不審に思っていたが、まあ心配する必要はない。これ以上説明するとネタばらしになってしまうからここで止めておくが、巻末に収められた作者の「創作ノート」によれば、書名に悩んでいたところに放たれた奥様の助言がそのまま書名に採用となったという。「例によって題がうかばずに七転八倒していると」
とあるので、鮎川さんは書名を付けるのに苦労するほうの作家だったらしい。
松本清張とくらべると、タイトルが直截的な印象を受けてしまうのも、そうした個性に由来するのかもしれない。以前も思ったが、松本清張のように抽象的すぎるほうがかえってミステリのタイトルとしてふさわしいのかもしれない。トリック自体は、東京という大都市の特性が生かされているもので、その着眼点に感服したのだった。